💡この記事のポイント
✅投資初心者が間違いがちな6つの誤解を解消
✅破産したくない!お金がないから株が買えない!
✅知識がないから出来ない!投資信託って低コストを選べばいいんでしょ?
✅株って副業になる?税金は高いんでしょ?
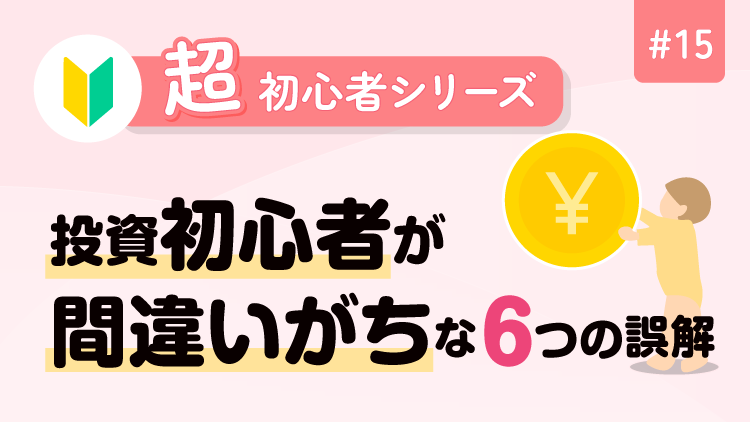
✅投資初心者が間違いがちな6つの誤解を解消
✅破産したくない!お金がないから株が買えない!
✅知識がないから出来ない!投資信託って低コストを選べばいいんでしょ?
✅株って副業になる?税金は高いんでしょ?
誤解したままで足踏みしていませんか?
間違い1.損失が怖い!破産したくない!
間違い2.お金がないから株が買えない!
間違い3.知識がないからできない!
間違い4.投資信託って低コストを選べばいいんでしょ?
間違い5.株って副業になる?
間違い6.税金は高いんでしょ?

NISA(少額投資非課税制度)などを活用して、株式や投資信託などの投資にチャレンジする人が増えています。昨今では、モノやサービスの価格が上昇していることもあり、安全確実な銀行預金だけでは資産価値は目減りしていく一方です。
でも、投資の初心者や未経験の人には色んな不安や誤解があるのも当然です。そんな誤解や漠然とした不安で、資産形成/資産運用をはじめることに足踏みしていませんか?
そこで今回は、そんな投資初心者が間違いがちな誤解をまとめて解消しましょう。

「投資って怖そう」「大損して破産してしまわないか」と不安ではじめられないという人もいらっしゃるようです。
実際には、例えば株式や投資信託を買って損をする最大の金額は、投資した金額までに限られています。
株を買って一番損失が大きくなるケースは、株を買った会社が倒産してしまうこと。この場合、株式市場では、売りたくても売れない状況になってしまうことも多く、最悪のケースでは投資資金がゼロになってしまいます。
ですので、投資初心者のうちは、時価総額が大きく(会社の規模が大きい)、業績が安定している会社を選ぶのがオススメです。
ちなみに、投資信託の場合は、複数の会社や金融資産に分散して投資していますので、原則、投資資金のすべてを失ってしまうことはありません。
資産運用では「分散投資」を行うことで、一度に大きな損失を出さないようにすることができますので、「怖くて一歩が踏み出せない」という人はバランスファンドなどの投資信託からはじめてみるのがよいでしょう。

「株なんて買う大金は持っていない」「投資はお金が貯まってから」と考えている方も多いようです。
たしかに一昔前までは、株式投資はお金持ちだけのものというイメージもありました。中には最低売買単位分を買うだけでも何百万円も必要な銘柄もありますから当然でしょう。
でも、今では少額から投資できるようになりました。PayPay証券では、投資信託や日本株や米国株が100円以上1円単位で購入できますので、投資初心者も気軽に資産運用にチャレンジすることができます。
お金が貯まってから、お金に余裕ができたら、というのも良いですが、少額からコツコツつみたてて、若い内から資産運用を学びながら行っていく方が、知識や経験を重ねることにも繋がります。
また、少しでも早くはじめることで「長期投資」のメリットを活かすこともできます。
まとまったお金がなくても、資産形成をはじめる価値があるはずです。

「株とかなにも分からない」「なにを買えばいいのか、なにからはじめればいいのか分からない」という方もいらっしゃるでしょう。
誰でもはじめは初心者で、知識も充分あるわけではありません。少しずつでも学びながら少額からはじめて行くことができるのが資産運用です。知識はあるにこしたことはありませんが、知識があるからといって絶対上手くいくわけではありません。
自分のよく知っている会社や業界の株を買う、投資信託を買って運用はプロに任せる、株価指数などに連動するインデックスファンドを買う、などあまり知識がなくてもできることがあります。
なにを買えばいいか分からないという方にも「おまかせ運用」という、2つのファンドから選ぶだけで、100円からカンタンにつみたて投資ができるサービスもあります。
もちろん、知識は徐々にでも身につけていっていただきたいですが、そのためには実際に経験することでしか得られないものが沢山あります。
また「資産運用の1st STEP」でも分かりやすく学んでいただけるようコンテンツをお届けしますので、ぜひご活用ください!

「投資信託ってコストの安いインデックスファンドを選べばいいんでしょ」「コストの安いファンドを選べば間違いない」と思っている方も多いのではないでしょうか。
投資信託は、運用のプロである投信会社があなたに代わって運用してくれる金融商品です。そのため、自分で株を買う場合とは違って運用や管理してもらうためのコストが必要です。
例えば、信託報酬は投資信託の保有額に対して年率で発生する費用です。また、信託財産留保額は、投資信託を解約(売却)する際に投資家が負担する費用です。これらのコストは投資信託によってまちまちに設定されています。
もちろん、買う側からするとコストは安いに越したことはありませんが、コストが安いということはその投資信託にはそれだけ手間暇やコストがかかっていないということでもあります。
また、コストの高い低いで運用成績が決まるわけではありませんから、コストが高いからと言って好成績が約束されるわけではありません。また、いくらコストが安くても運用成績が悪ければ意味がありません。
ファンド選びは、ご自身がどのような投資を行いたいのか?で考えましょう。リスクが高くても積極的なリターンを求めたいのか、安全な資産運用を目指したいのか、ほどほどのバランスを考えて行いたいのか、それらに合わせて選ぶべきです。
一般的にコストの安いインデックスファンドと、プロのファンドマネージャーが運用方針に基づいて最善な運用を目指すアクティブファンドでは、それぞれに特徴や良さがあります。ご自身の資産運用の一部にはどれが向いているか、組み合わせるか、などを考えてコストだけではなくトータルで選ぶと良いでしょう。

「会社の就業規則で副業が禁止されているので、株式投資はちょっと」と考えている人もいるかもしれません。
でも、一般的に株式投資は副業には当たりません。中には、副業ではなくとも証券会社や新聞社のように株式の取引が社内ルールで禁止されているケースもありますが、それ以外の社会人の方は、基本的にOKと考えていいでしょう。心配であれば、会社の関連部署などに確認してみましょう。
株式投資で一定以上の利益が出ていれば、税金が増えて会社に知られるかもと思う人もいるかもしれませんが、口座開設時に「源泉徴収ありの特定口座」を選んでおけば、利益から自動的に税金が引かれます。原則、確定申告も不要で、納税は証券会社が代行して行ってくれますので、通常は会社に知られることはありません。
さらに、NISA口座であれば、そもそも株の利益に対する税金はゼロとなっています。
もちろん、本業に支障が出るほどのめり込んでしまったら、副業以前にいかがなものかと思いますから、なにごともバランスが重要です。

「投資って儲かっても税金が高いんでしょ?」「儲かっても税金取られるのはイヤだな」と思っている方もいるかもしれません。
しかし実は、株式投資や投資信託で得た利益への課税は比較的高くはありません。
株式投資の利益には、配当と譲渡益(売却益)があり、それぞれに所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%(2037年12月31日まで)の合計20.315%が徴収されることになります。投資信託も譲渡益は同じで、普通分配金は株の配当と同じ、「元本払戻金(特別分配金)」は非課税となる点だけが異なります。
例えば、所得税の最高税率は45%です。課税される所得金額が330万円の場合の所得税率が20%ですから、それとほぼ同じです。株式投資でいくら儲かっても税率は変わりません。
また、年間の損益を通算し、トータルで損をしている場合には納税の必要はありません。さらに、年間を通じて利益より損のほうが大きい場合には、確定申告で損失の繰越控除を受けることもできます。これは、その年の損失を翌年以降の利益と相殺することで、税負担を軽減できる制度です。毎年確定申告をすれば、最長3年間まで損失を繰り越せます。
なお、NISAの場合、利益に対する税金はかからない一方で、損をした場合の損益通算はできません。
20.315%の税金が高いと感じるか、低いと感じるかは人それぞれですが、どんなに利益が出ても約20%の税金というのは、所得税などと比較すると考えようによっては低いと言える面もありそうです。
<最新ランキング&銘柄一覧>
・配当利回りランキング【米国株/日本株】
・NISA人気銘柄ランキング【投資信託/米国株/日本株】
・アナリストの目標株価を下回る米国株一覧
・PBRが1倍割れしている日本株一覧
記事作成日:2025年1月31日
金融商品取引法に基づく表示事項
●本資料をお客様にご提供する金融商品取引業者名等
商号等:PayPay証券株式会社 https://www.paypay-sec.co.jp
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2883号
加入協会:日本証券業協会
指定紛争解決機関:特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
●リスク・手数料相当額等について
証券取引は、株価(価格)の変動等、為替相場の変動等、または発行者等の信用状況の悪化や、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために元本損失が生じることがあります。
お取引にあたっては、「契約締結前交付書面」等を必ずご覧いただき、
「リスク・手数料相当額等(https://www.paypay-sec.co.jp/service/cost/cost.html)」について内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお取引ください。
免責事項等
●本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を目的とし、投資勧誘を目的としたものではありません。投資の最終決定はお客様ご自身の判断で行ってください。
●本資料は、信頼できると考えられる情報源に基づいて作成されたものですが、基にした情報や見解の正確性、完全性、適時性などを保証するものではありません。本資料に記載された内容は、資料作成日におけるものであり、予告なく変更する場合があります。
●本資料に基づき行った投資の結果、何らかの損害が発生した場合でも、理由の如何を問わず、PayPay証券株式会社は一切の責任を負いません。
●電子的または機械的な方法、目的の如何を問わず、無断で本資料の一部または全部の複製、転載、転送等は行わないでください。